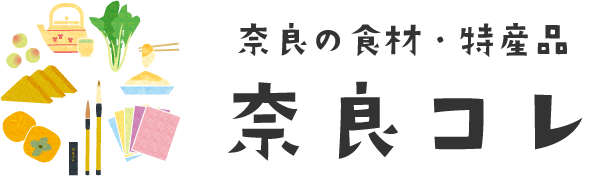検索結果
カテゴリ:
フルーツ
産地・エリア:
季節:
キーワード:
19件
 … 大和のこだわり野菜
… 大和のこだわり野菜
 … 大和の伝統野菜
… 大和の伝統野菜
すいか
〔ウリ科スイカ属〕
県内で本格的にすいかの栽培が始まったのは明治時代。現在でも全国のすいかの多くが県内の種苗会社で品種改良された種子から作られている。
| 主な産地 | 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村 |
|---|---|
| 主な季節 |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 特徴 | 奈良県が品種改良を積極的に行い、育成した「大和」種が人気を博し、大和西瓜はブランドになっていった。現在でも全国のすいかの多くが県内の種苗会社で品種改良された種子から作られている。 |
| 歴史 |
すいかはアフリカが原産地で、ヨーロッパ、シルクロードを通り、中国を経て日本へと伝わった。奈良の川西町の糸井神社には、およそ150年前に奉納された絵馬に、たるで冷やしたすいかを切り売りする祭りの様子が描かれていることから、販売用のすいかが栽培され、庶民の食べ物であったと考えられている。
すいか栽培は奈良の風土にあっており、明治から大正時代にかけて広く栽培されていた。奈良ですいかの栽培が盛んになったのは江戸時代末期。当初は、「権治」と呼ばれるすいかが栽培されていました。その後、アメリカ・カリフォルニア大学から導入された「アイスクリーム」と呼ばれる品種と自然交配し、奈良県産のすいかとして「大和西瓜(やまとすいか)」が誕生。これが、近代まで続くすいか品種の基礎となったといわれている。 |
黄金まくわ(おうごんまくわ)

〔ウリ科キュウリ属〕 ☆素朴な味わいが、再び人気☆
平城宮跡から種子が発掘され、「万葉集」の中でも山上憶良が「瓜食めば(うりはめば)…」と詠んでいるように奈良時代から庶民の間でも食べられていた。ほのかな甘みと黄金色の果皮が美しい。

| 主な産地 | 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、宇陀市、山添村、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、曽爾村、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、王寺町、広陵町、河合町、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村、東吉野村 |
|---|---|
| 主な季節 |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 特徴 | ほのかな甘みと黄金色の果皮が美しい。昭和初期から奈良県が品種育成を進め栽培面積が拡大したことにより、奈良のまくわが市場を席巻きした。県内ではマッカの名で親しまれ、現在では、主に自家消費用として栽培されている。お盆のお供え物として使われることが多い。 |
| 歴史 |
藤原京跡や平城京跡から種子が発掘され、「古事記」や「万葉集」の中の、山上憶良が「瓜食めば…」と詠んでいるように、奈良時代から庶民の間でも食べられ、プリンスメロンやネットメロンが普及する前、昭和30年代までは、甘く、香りの良いまくわうりは高級食材として愛され、奈良県内だけでなく全国各地で多くの地方品種が栽培されていた。中でも優れた特徴を備えている奈良のまくわうりが「黄金まくわ」の名で大和野菜に認定。その懐かしく素朴な味わいに、再び人気が集まっている。
|
さくらんぼ
〔バラ科サクラ属〕
さくらんぼといえば山形が有名だが、県内の美味しいさくらんぼは山形より一足早く楽しめる。
| 主な産地 | 天理市、桜井市、五條市、下市町 |
|---|---|
| 主な季節 |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 特徴 |
生産量はまだ少ないが、直売所などに出回り、佐藤錦や高砂などの品種を味わうことができる。コンポート(シロップ漬け)がおすすめ。
<知恵袋> おいしい食べ方 さくらんぼのコンポート(シロップ漬け)。せっかくの鮮やかな赤色は煮ると色が抜けてしまうため、ボイセンベリーやラズベリーを入れて一緒に煮る。ジャム作りも同じ。お菓子のトッピングにもなる。 |
| 歴史 | 奈良のさくらんぼは、全国生産量の8割を占める山形より2週間早く収穫できる。平成19年から本格的な販売がスタートした新しい特産品。 |
梅(うめ)
〔バラ科サクラ属〕
古来、花といえば梅であった。南朝の貴族達を慰めた賀名生梅林、松尾芭蕉が愛で句を残したと伝えられる月ヶ瀬舞林などの名勝は、今は美味しい梅の産地でもある。
| 主な産地 | 奈良市、五條市、下市町 |
|---|---|
| 主な季節 |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 特徴 |
梅はレモンに匹敵する高濃度のクエン酸を含み、その芳醇な香りとともに、梅の個性を形作っている。奈良では6月上中旬に収穫する鶯宿(おうしゅく)、6月中下旬の白加賀(しらかが)、6月下旬から7月初旬の南高(なんこう)などが作られ、梅酒や梅干しに加工されている。
<知恵袋> 梅干しの上手な漬け方 腐りにくいはずの梅干しを家庭で作るとよくカビが生えて駄目になることがある。カビの生育には酵素が必要であり、漬け汁から浮いて露出した部分によく発生する。そこで、シソや果実を漬け汁にしっかり沈めるようにすればカビが生えにくくなる。 |
| 歴史 | 南朝の貴族たちを慰めた賀名生梅林、松尾芭蕉が愛で、句を残したと伝えられる月ヶ瀬梅林などの名勝が、今の梅の産地となっている。 |
いちじく
〔クワ科イチジク属〕
世界最古の農作物の一つ。「聖書」をはじめ、様々な神話に登場する。日本へは約400年前に渡来。以降、新品種や独特の栽培技術が生まれ、美味しい果実が生産されている。
| 主な産地 | 大和郡山市、明日香村、下市町 |
|---|---|
| 主な季節 |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 特徴 |
そのまま食べてももちろん美味しいですが、グラッセなどの加工品も生産されている。
大和郡山市を中心に水田にで植栽され、現在は出荷量で全国7位の産地である。 <知恵袋> おいしい食べ方 いちじくに豊富なアントシアニンは、酸性であざやかに発色する。ジャム等を作る際に美しく仕上げるには、①一度に大量に煮込まない、②加熱しすぎない、③レモン汁などの酸を仕上げ前に添加するとよい。 |
| 歴史 | 世界最古の農作物の一つ。「聖書」をはじめ、さまざまな神話に登場する。日本には約400年前に渡来。県内で本格的な栽培が始まったのは大正時代。 |
ぶどう
〔ブドウ科ブドウ属〕
「古事記」で最初に記述のある果物であり、高松塚古墳出土の海獣葡萄鏡の文様など、ぶどうの歴史は古い。本格的な生産は、明治以降の新品種導入からだ。
| 主な産地 | 天理市、五條市、平群町、明日香村、河合町、下市町 |
|---|---|
| 主な季節 |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 特徴 |
ぶどうの赤や黒の色素はアントシアニンというポリフェノール。種子にも別のポリフェノールがあり、ワインに深みを与える渋みのもととなっている。
デラウェアは小粒で程よい酸っぱさと甘みのバランスが取れた味わいが特徴。巨峰は大粒で甘みが強く優しい酸味があり「ぶどうの王様」と呼ばれている。 <知恵袋> ぶどうの赤や黒の色素はアントシアニンというポリフェノールだ。種子にも別の種類のポリフェノールが多近年は健康機能性が研究され、その成果が期待されている。近年は健康機能性が研究され、その成果が期待されている。 |
| 歴史 |
県内には明治末のデラウェア導入から栽培が始まった産地が多い。その後、昭和30年代に種なしぶどうが誕生し、一世を風靡する。現在はデラウェアのほか、シャインマスカットなど美味しく多彩な品種が生産されている。また、令和4年には奈良県で初のワイナリーが設置され、ワイン用のぶどう栽培も行われている。
|
梨(なし)
〔バラ科ナシ属〕
梨の歴史は古い。中国西部で生まれた梨は、やがて海を渡り日本梨の系統になった。持統天皇が栗や芋などとともに栽培を奨励するなど、歴史的にも重要な果物の一つだ。
| 主な産地 | 五條市、斑鳩町、大淀町 |
|---|---|
| 主な季節 |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 特徴 |
品種によりさまざまな食感や甘みが楽しめる。青梨の代表的な品種である二十世紀はみずみずしくてさっぱりとした甘みが特徴。
<知恵袋> おいしい食べ方 美味しい梨を選ぶには、同じ品種ならしっかり育った大きめの果実であること、表面に目立つ傷などがないこと。「利尻柿頭(なししりかきあたま)」というように、梨は枝に近い方が甘く美味しい。なるべく薄く皮を剥いて食べるとよい。 |
| 歴史 |
日本のナシの歴史は古く、飛鳥時代には持統天皇が栽培を奨励したといわれている。奈良県では幕末の安堵村(現在の安堵町)で栽培が始まり、明治以降、大淀町や五條市に広がって、現在の梨産地が形成された。市場出荷はほとんどされず、明治以来続く直接販売と、観光農園を主体に、高品質の梨が供給されている。
|
柿(かき)
〔カキノキ科カキノキ属〕
奈良の柿の歴史は古く、「正倉院文書」にも記録が残る。果実だけではなく、柿渋や柿のへた、柿の葉すしの葉など、捨てるところのない果樹として古くから愛されてきた。
| 主な産地 | 天理市、五條市、御所市、下市町 |
|---|---|
| 主な季節 |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 特徴 |
奈良県は全国第二位の生産量を誇る大産地だが、最大の特徴は出荷期間の長さにある。生産量日本一のハウス栽培や冷蔵保存技術と複数の品種を組み合わせ、7月〜1月の半年間柿を出荷することができる唯一の産地である。甘味と食感をダイレクトに感じることができる。熟し具合によっても味や食感が変わる。
<知恵袋> 渋柿 刀根早生などの渋柿は、渋抜きをすると生の果実のままおいしく食べられる。スーパーに並ぶ渋柿(干し柿用除く)は、すでに渋抜きされているもの。家庭で渋抜きをする場合は、柿のへたを焼酎に浸してビニール袋に入れ、温かい部屋で数日置くとよい。 |
| 歴史 | 奈良の柿の歴史は古く、「正倉院文書」にも記録が残る。 |
刀根早生(とねわせ)
〔カキノキ科カキノキ属〕
伊勢湾台風で樹が折れたのがきっかけとなった突然変異種。1980年の品種登録後、瞬く間に全国に普及し、今や日本の柿生産面積第3位を占める柿の代表品種だ。
| 主な産地 | 天理市、五條市、御所市、下市町 |
|---|---|
| 主な季節 |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 特徴 |
天理市の平核無(ひらたねなし)の畑から発見された渋柿。平核無にそっくりだが、成熟が早く高温でも良く色づくため、ハウス栽培も盛んに行われている。奈良県のハウス柿生産量は日本一であり、その品質も優れていることから、2018年に奈良県プレミアムセレクトとして県が認証(ハウス柿のみ)。
|
| 歴史 |
昭和34年に近畿地方を襲った伊勢湾台風は、天理地域の柿園にも大きな被害を与えた。柿の栽培農家は復興を目指して、翌年の春に主要な枝が折れた樹に、平核無を腹接ぎという方法で接ぎ木をしたところ、刀根さんが接ぎ木した樹の中の一枝が他よりも早く色づく果実を実らせたことがきっかけ。1980年の品種登録後、瞬く間に全国に普及し、今や日本の柿生産面積第3位を占める柿の代表品種となった。
|
平核無
| 主な産地 | 天理市、五條市、御所市、下市町 |
|---|---|
| 主な季節 |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 特徴 | 果実は明るいオレンジ色で、形は扁平な四角形。たねがなく食べやすい柿。たねなし柿の代表的な品種。味はやわらかくなめらかな食感が特徴。 |
| 歴史 |
平核無(ひらたねなし)は昭和10年頃に栽培されはじめたが、当時、脱渋(渋抜き)技術が不安定だったことから栽培面積は伸び悩んでいた。昭和30年頃に共同脱渋施設が作られたことから脱渋技術が安定し、商品性が大きく向上したことに加え、富有柿より収穫時期が早く収量も多いことからひろがっていった。
|
富有(ふゆう)
〔カキノキ科カキノキ属〕
明治時代に登場後、今も日本で最も多く生産されている柿のロングセラー。
| 主な産地 | 天理市、五條市、御所市、下市町 |
|---|---|
| 主な季節 |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 特徴 | 良く色づいた果実が美味しく、優れた品質をさらに厳選した奈良県プレミアムセレクトもある。氷温で長期間保存することもできる品種なので、冷蔵柿として1月下旬まで美味しく食べられる。 |
| 歴史 | 富有柿が奈良県で栽培されたのは、明治末から大正初めで、現在の五條市に入ったといわれいてる。大正11年に大寒波があり、当時経営の中心であったミカンが大被害を受けたことがきっかけで、富有柿の植栽が進んだ。現在、奈良県は富有柿生産全国第1位を誇っている。 |
御所柿(ごしょがき)
〔カキノキ科カキノキ属〕
松尾芭蕉や正岡子規ら文人に愛された柿。幻の柿として今も求める人が多い。
| 主な産地 | 御所市 |
|---|---|
| 主な季節 |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 特徴 | 果実は150gほどのものが多く、小ぶり。扁平で方形をしていて、果頂部が緩やかに尖っている。完全甘柿の原種であるといわれいてる。果肉は糖度が17~20度と高く、粘り気のある肉質であることから「天然の羊羹」と呼ばれている。生理落果しやすく、栽培が難しい。 |
| 歴史 |
300年以上の歴史をもつ御所周辺で生まれた甘柿で、「その味わい絶美なり。もって上品となす」と江戸時代の書物「本庁食鑑(ほんちょうしょっかん)」に記されるなど、全国に「美味しい柿」として名を馳せた。品質が優れていることから、昭和の初めまで天皇家に献上されていた。富有などの新品種の出現によって栽培面積は激減した。
|
いちご
〔バラ科オランダイチゴ属〕
1962年から18年間、作付面積が全国第3位の大産地だった奈良のいちごは、今でも県を代表するくだものだ。
| 主な産地 | 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、広陵町、河合町、大淀町、下市町、天川村 |
|---|---|
| 主な季節 |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 特徴 |
爽やかな香りと口いっぱいに広がる甘酸っぱい味わいが特徴。品種によって、糖度や味わい、食感が違う。 <知恵袋> おいしい食べ方 いちごは先端に向かって甘みが増すため、ヘタの方から食べると、最後に口に甘味が残って美味しく味わえる。 |
| 歴史 |
奈良県は1962年から18年間、作付面積が全国第3位の大産地だった。本来いちごの旬は春であるが、クリスマスにも出荷できるように昭和40年頃に技術革新がなされたが、その技術の多くが奈良県が開発したもの。奈良のいちご農家の技術力は高く、品質の良いイチゴが今でも生産されている。
|
アスカルビー
〔バラ科オランダイチゴ属〕
奈良のいちごの代名詞ともいえるアスカルビー。丸みをおびた形は、万人から愛される宝石のような珠玉の一粒。
| 主な産地 | 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、香芝市、葛城市、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、田原本町、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、広陵町、河合町、大淀町、下市町 |
|---|---|
| 主な季節 |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 特徴 | 丸みのある円錐形で、粒ぞろいがよく、水分が豊富で口に含んだ瞬間に果汁が溢れ出るジューシーさが幅広い世代に親しまれている。観光農園では完熟のアスカルビーを食べることができる。 |
| 歴史 | 奈良県が育成し、2000年に品種登録されたロングセラーいちご。 |
古都華(ことか)
〔バラ科オランダイチゴ属〕
口中に広がる濃厚な味わいは、一度食べると忘れられない。
| 主な産地 | 奈良市、大和高田市、大和郡山市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、川西町、田原本町、御杖村、高取町、明日香村、上牧町、広陵町、河合町、大淀町、下市町 |
|---|---|
| 主な季節 |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 特徴 |
「いつ食べてもおいしい」いちごを目指して奈良県が育成した品種。糖度と酸度が高く、味わいは濃厚で、フルーティな甘い香りが特徴。濃い赤色で、果肉はしっかりとしていて、食べ応えがある。県内でしか栽培されていない希少価値の高いちょっと贅沢ないちご。 |
| 歴史 | 古都華は奈良県農業試験センターが育成し、2011年に品種登録された奈良県生まれのいちご。平群町は古都華の栽培面積1位を誇る産地。 |
珠姫(たまひめ)
〔バラ科オランダイチゴ属〕
一口では食べきれない大きな果実が特徴。
| 主な産地 | 奈良市、大和高田市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、葛城市、平群町、三郷町、田原本町、高取町、明日香村、広陵町、河合町 |
|---|---|
| 主な季節 |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 特徴 | 卵サイズの果実は見た目のインパクトが大きい。酸味が少なく、優しい味わいは、子どもからお年寄りまで万人に好まれる。 |
| 歴史 | 2019年に品種登録出願し、2024年に品種登録された品種で栽培面積は少ないが、売り場では存在感を放っている。 |
奈乃華
「古都華」から産まれたニューフェイス。奈良に咲く「華」をイメージして名付けられた。
| 主な産地 | 奈良市、大和高田市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、葛城市、三郷町、斑鳩町、三宅町、田原本町、高取町、明日香村、上牧町、広陵町、大淀町 |
|---|---|
| 主な季節 |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 特徴 | 果皮が硬く、痛みにくい。贈答用としても使われる。親の「古都華」が持つ、甘味と酸味のバランスの良さが顕在。 |
| 歴史 | 表面(果皮)がしっかりしているので、暖かい季節になっても日持ちがよく、味は甘みと酸味のバランスが良好。2020年より「奈乃華」の名前で発売されたばかりの品種。 |
ならあかり
| 主な産地 | 奈良市、大和高田市、天理市、橿原市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、葛城市、平群町、三郷町、斑鳩町、川西町、田原本町、明日香村、広陵町 |
|---|---|
| 主な季節 |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 特徴 | 県育成の他品種(アスカルビー、古都華)よりも収穫開始期が早く果形の揃いが良い。糖度が比較的高く安定しており、酸度が高く、すっきりとした甘さ。 |
| 歴史 |
「古都華」と「とちおとめ」の交配から得られた奈良県育成系統に、「古都華」と「かおり野」の交配から得られた奈良県育成系統を交配し、2014年に得られた約4,500株の中から選抜した。 また、2021年には品種登録出願された。 |
ジャバラ
| 主な産地 | 下北山村 |
|---|---|
| 主な季節 |
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
|
| 特徴 | 強い酸味と独特の苦味が特徴。果汁が豊富。とても酸味が強いため、みかんのようにそのまま食べるのは難しい。ジャバラリキュールやジャバラ果汁などが販売されている。 |
| 歴史 | 和歌山県北山村から全国に広まったのをきっかけに、栽培を開始。「邪」を「祓う」ことから『ジャバラ』と名付けられた。 |